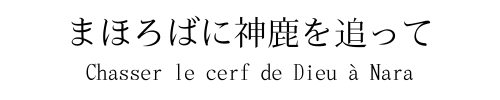2025年9月25日、ならまちの鹿の舟にて宇都宮弘子先生の草木染レッスン、今回で3回目。念願の二藍(ふたあい)、藍の生葉と紅花の二色の変化を味わう、初歩から一歩進んだ紫色の重ね染めに挑戦。
私は前もって先生の作品を確かめていたので、藍の生葉のシアンブルーと紅花のマゼンタピンクの目の覚めるようなヴィヴィッドカラーのグラデーションを活かした、天女がまとう羽衣のようなショールを作ることが目的。
さても、めでたく念願叶えた備忘録、以下となります。

先ずは、藍の生葉染めから。これは、藍の花の咲く夏場にしかできない染めなのです。
普通、藍は藍色の名の通り、とても深い青の色を指します。その藍色は、葉っぱを乾燥させて微生物で発酵させた「建て染め」によって通年にかけて得られる色なのです。
この季節だけの藍の色、シアンブルー、7月のレッスンの課題でしたが日程が合わず。しかし今日の二藍染めは、それが紅花染めと同時に楽しめる、二度おいしいレッスンなのです。

採れたての藍の葉っぱを千切って、水をひたひたに入れて、ミキサーにかける。藍は、先生がアトリエの東吉野村で栽培されている藍です。

搾りたての藍の生葉は、緑色。この染液にすぐ、布を浸して染めなければいけません。藍の生葉染めは、媒染剤を用いず、過熱もせず、空気中の酸素による化学反応で染まるのです。ただし、時間が勝負。

この美しいシアンブルー、この色だけでもう満足してしまいそう。右端は、藍の花です。捨てるには惜しい愛らしさ、持ち帰りたい方に先生は譲っていらっしゃいました。

二藍とは、通常、藍と紅花の合わせ色の紫色を指すので、私以外の方は布全体に藍の染液をくぐらせておられました。私は、グラデーションを際立たせるため、藍で片側を深く染め、徐々に薄まらせ、もう片側には藍をくぐらせませんでした。

さて、お昼ごはん。ならまち「鹿の舟」の観光案内兼イベントブース「繭」の特別室でのお食事。秋めいた蒸し野菜のメインがおいしい、相変わらず健康的で滋味深い献立。
二藍とは。古代日本、そもそも草木染の原料の総称が「藍」だったらしく、大陸の騎馬遊牧民匈奴の名産だった紅花を、匈奴を制した後漢が専売したことにより、「呉(くれ)」から来た「藍(あい)」と紅花を「くれない」と呼んだことから、藍と紅花、「ふたつのあい」すなわち「ふたあい」と呼ぶようになったと。
奈良県桜井市の纏向遺跡で紅花の遺物が発掘されたことから、卑弥呼が魏へ献じた絳青縑(こうせいけん)つまり赤と青の錦との関わりも示されたとの、先生の語りは、まるで奈良大学通信教育部の講義を受けているようで、私、うっとりと気が遠くなりました。
私は、卑弥呼がいただろう奈良で、卑弥呼と同じく藍と紅花を愛でているのだと。

さて、午後からは、二藍のもうひとつの藍、紅を染める。しかし、紅花の赤い色の抽出はおそろしく手間がかかるため、8月の紅花の単独染めのレッスンで残った染液を浸した布を用いることに。これを、強アルカリの灰汁でもって、色をもみだすのです。

もみだした染液ではアルカリ性のままなので、布に色は染めることはできない。それに酢をかけて中和させると黄色い染液が赤く変化し、布に着色できるようになる。
草木染は、おもいっきり、化学なのです。

さて、私の藍で染めた布、藍をくぐらせていない生地のままの片側を紅花の染液にひたしました。あっと言う間に、こんな目鼻立ちのはっきりとしたピンク色に染められて。

右端が私の染めた二藍。私だけが、シアンブルーとマゼンタピンクと紫のグラデーションがはっきりとしたショールになり、他の参加者の皆さんに「なんてなまめかしいの! 天女の羽衣みたい!」と褒められてしまいました。

なまめかしいとは、やはり紅花のピンク色が因子なのだと思いました。こんな綺麗なピンク色、ちょっと人外めいていますし。

先生も「二藍染め、なんとも艶っぽい、ほんとうに美しい」と称賛。

自画自賛してしまわざるを得ない、こんな美しい色の重なり、水色と紅色、まるで蓮の花のような。

風まで薫らせて、色づかせるような。

天女から羽衣を奪ってしまいたくなる気持ち、わかってしまった。

もう私には天女が見えてしまう。ほら。そこに。

総勢8名の二藍のショール、薔薇のように巻いてみて、壮観。

私の二藍の薔薇は、真ん中のピンクが目立つもの。
ああ、私は草木染の虜、もはや。
天女が皆を虜にするように。
あなたはあの時、ぼくに言いましたね、「天女を妻にした男は幸福だったろうか、それとも、不幸だったろうか」って。
ぼくはきっと、幸福だったろうと思いますよ。
きっと、後悔はしなかっただろう、と。
吉田秋生『吉祥天女』