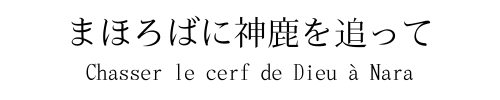我が家は近鉄ケーブルネットワークに加入してテレビを視聴しています。
いつも楽しみにしているのが、『大和の車窓』という運転席からの眺めの近鉄電車路線を30分間延々と流してくれる、ちょっとした旅気分の番組です。

これは橿原神宮前駅から大阪阿部野橋駅までの南大阪線。
葛城市、尺土駅あたりの風景、尺土駅は私の実家の最寄り駅です。
左手、長尾神社の鳥居です。
そして目の前、二上山、ふたかみやま、私の原風景です。

故郷の景色を眺めていると、仁徳天皇皇后、葛城磐之媛(かつらぎのいわのひめ)、私が心ひそかに敬愛してやまない、孤高の女王について語りたくなりました。
私はこのとおり、葛城の文化圏で生まれ育った者ですが、二上山のふもとはほんの入り口、葛城の本陣は奈良盆地西南部の御所市にこそあり。
そこが、磐之媛の産土(うぶすな)です。
葛城磐之媛は大王の正妃など二次的な存在ではなく、おそらく古代豪族葛城氏を一手に担う、女王に等しい存在だったと思われます。
和賀美賀本斯久邇波 迦豆良紀多迦美夜 和藝幣能阿多理
吾が見が欲し土(くに)は葛城高宮の吾家(わぎへ)の辺り
私が見たいのは、葛城の、高宮の、私の家、私の故郷。
『古事記』下つ巻・仁徳天皇
菟道稚郎子(うじわきいらつこ)の同母妹である八田皇女(やたのひめみこ)を新しく妃に迎えた夫、仁徳天皇のもとから磐之媛は去っていきました。
大王である夫は、正妃の自分と同じ立場に、その若い皇女を置こうとしたのです。
誰かと肩を並べるなど、潔癖な磐之媛には認められるはずがなかったのです。
大王みずからの迎えにも、磐之媛は応じはしませんでした。
そして、ひとり、葛城から遠く離れた山背筒城宮で、誇り高い葛城の女王はこの世を去りました。
私は、佐紀盾列古墳群のヒシアゲ古墳に磐之媛が眠っているとは思っていません。
きっと、その気高い魂ごと、葛城高宮の産土に還らせてあげた、御所市の古墳群のひとつに磐之媛は眠っているにちがいない、私はそう堅く信じているのです。
それが、最も高潔な女、葛城磐之媛に対する、仁徳天皇からのせめてもの餞だと。
もしそうでないとすればあまりにも、むごい。

速総別王(はやぶさわけのみこ)と女鳥王(めどりのみこ)の叛乱の終焉、追手の将軍の山部大楯連(やまべのおおたてのむらじ)は、土くれにうずもれた皇女のまだ温かい遺体の手首から、血にまみれた玉釧(たまくしろ)を奪い、その妻に与えました。
よりにもよって豊明節会(新嘗祭)に大楯連の妻は、女鳥王の玉釧を腕に巻いて出向きました。
磐之媛はそれを伺うと同時に、大楯連の妻を宴席から退かせ、残った大楯連へ向かい、冷然と言い放ちました。
其王等 因无禮而退賜 是者無異事耳 夫之奴乎 所纒己君之御手玉釼 於膚熅剥持來 卽與己妻
其の王等、礼旡きに因りて退け賜へる。是は異しき事無くこそ。
夫れの奴や、己が君の御手に纒かせる玉釧を、膚も熅けきに剥ぎ持ち来て、即ち己が妻に与へたり。速総別王と女鳥王は、大王に無礼を働いたから廃された。これは何もおかしなことではない。
しかし、おのれは、王族の者がその身に常にまとわせていた玉釧を、まだ温もりの残る屍から剥ぎ取り、おのれの妻に与えるとは。『古事記』下つ巻・仁徳天皇
恥を知れ。
そう謂わんばかりに、磐之媛は大楯連に死罪を告げました。
是は異しき事無くこそ。
それは、叛乱を制圧して当たり前、それが正規な意味でしょう。
しかし、若者が叛乱を起こすことこそ自然、そうとも私には意に介せました。
磐之媛は、敗れた者を粗末に扱わない、フラットな見識を持つ聡明な女性でした。
磐之媛は見知っていたのでしょう、女鳥王がどれほどその玉釧を大切にし、我が分身と見なし、終ぞ肌身から離さなかった、その一途な姿を。
女鳥王の玉釧、人を狂わせるほど美しく魅力的だったのでしょう。
持ち主の女鳥王と、同じく。
そして、大楯連はその妻を、たいへん愛していたのでしょう。
禍々しいほど美しい王族の玉釧、盗む気などなかった、魔が差した、ただ妻に喜んでほしかった。
そして妻も夫のために装いたかった、いちばんの公の場で、皆のまえで、夫の傍らで美しくありたかった。
ひとえに、夫のために。
だからこそ、磐之媛は断罪の場から退けた、これから罪人となる男の妻を。
夫が妻のために命を落とす無慚さを、その妻に、目の当たりに見せないよう。
だからといって、葛城の名代である女王は、敗者の無念を蔑ろになどしない。
否、蔑ろになど、できない。
その強靭な意志と、慈悲。

私は、磐之媛が好きなのです。故郷のように、心の芯にいつも在る。
その氷つく凍てつくような、きびしさ。
その幾重にも包み育まれた、やさしさ。
これが、古代豪族葛城氏の女王の、本懐です。
『古事記』は最高級の物語を私たちに伝えてくれています。
なかでも磐之媛の物語は、私の最愛の物語、人の哀しみと高潔さに満ちています。
私のたましいを、私のうぶすなへ、還らせて。
磐之媛のSwan Songを胸に抱え、私はいつも実家に向かいます。
我が女王、磐之媛、さあ共に帰りましょう、葛城へ。
私たちの、故郷へ。
死に瀕した白鳥がうたうという歌。その時、もっとも美しくうたうと古来伝えられる。転じて、ある人の最後につくった詩歌、歌曲など。また、俗語で、過ぎ去った昔の幸福などを詠嘆的に追憶することにも用いた。
精選版 日本国語大辞典