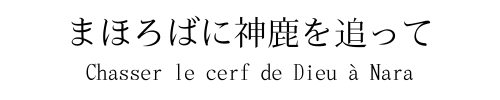2022年10月22日、私の原風景、葛城市の當麻寺へ。
ここは東大門。西の二上山に沈む夕陽を崇めるがゆえ、南ではなく東から向かうのです。
私は二上山ふもとの街、大和高田市生まれ。
実家から當麻寺までは自転車ですぐ。
私には二上山とその表舞台の當麻寺は、言いたいことが山ほどあって反って言葉にできない、そんな場所。

とても広い境内。実家にいるときの私には散歩道でした。
息子は赤ん坊のころに参った切りで、初見のように舞い上がっていました。

本堂の曼荼羅堂。
中将姫伝説と蓮糸曼荼羅、大津皇子の眠る二上山、聖徳太子の弟の麻呂子皇子、もろもろの符牒にちりばめられた、當麻寺、二上山、私の産土。

當麻寺によく通っていた10代のころ、病弱だった私は生きる気力がなく、どうやら中将姫に追い縋っていたようです。
うらやましかった、命がけで何かを掴めた中将姫が。
薄命であったけれども、甲斐ある人生だったはずだから。

手前は曼荼羅堂。ここは講堂。写っていない向かいの金堂には、白鳳仏の白眉の弥勒と四天王。
10代のころは中将姫ばかり追って、これら白鳳仏を看過していました。
四天王、シルクロードの鎧武者、でも顔つき体つきは本邦の名優、若山富三郎勝新太郎兄弟。その秘めた能力、静けさ。
鎌倉時代後補の多聞天、一言、役不足。脅すばかりが強さではないのだよ(シャア大佐?)。
若山富三郎勝新太郎兄弟、衒いがなく、真摯そのもの。白鳳時代に四天王のモデルとなったのは、正真正銘の武者だったのでしょう。
弥勒仏も、久々に拝見すると、こんな溌剌と引き締まった体躯だったのかと意識を洗われました。
なんて若いのか。
まさに白鳳時代に生まれた仏、と。

當麻寺の塔頭のひとつ、中之坊へ。だいぶ小さいころに参った切り。
手入れの行き届いた庭、白い大きな酢漿草(かたばみ)。

おー、ここにも三鈷の松が。
信貴山朝護孫子寺の玉蔵院にも三鈷の松はあります。

密教の法具「三鈷杵」に因んで、三つ葉の松を三鈷の松と言います。

東塔を借景に、庭園「香藕園」。
當麻寺は天平時代に築かれた塔が東西二塔とも、唯一現存しているのです。

素晴らしい。こんな見事な庭園だったのか。
小さいときって、庭の良さはわからないものなのでしょうか。それともよっぽど幼かったのか。

息子よ、塔が見切れてまっせ。
息子「人物がメインなの」との言。

石州流なのですね、ふむふむ。

1300年前から変わらない。

息子は池の蛙に夢中。

ぼん、お茶室も素敵だから見てね。

今日ここに来て良かった。

静かで、緑が豊かで。

ただ息子に見せたかった當麻寺。

主人、初見の中之坊に陶然。

客殿では、写仏や写経が体験できます。

書院でお茶をいただきました。
苦みのない極上の抹茶と、牡丹を象った落雁が相俟って。

「おいしいね」と主人と息子。
「来て良かったね」と私。
相席のご婦人お二人も私たちと同じ会話をされていました。
お二人は「お先に」と標準語でご丁寧にご挨拶されて退席され、「お気を付けて」と我々も返答しました。
幸せだな。
そう思いました。
みんなが幸せであればいいな。
そう思いました。

書院から眺める東塔。
ああ、これはいい。胸に染みる。

「ママはいいところで生まれたね」
まさか息子にそう言われるとは。
そうだね。
いいところだよ、二上山のふもとは。
死者や弱者を夕陽であたたかく包む、
そんなところだよ、當麻寺は。

中将姫、中将湯。
上村恭子さんのイラストが素敵な製薬会社ツムラさんのポスター。
欲しいな!

お茶席でいただいた花落雁を買って、花より団子。

中之坊の玄関。
息子の背の高さに主人、緊張。

中将姫は、その父の横佩大臣(よこはぎのおとど)藤原豊成の化身。不運な男であった豊成の、不運がそのまま人称化された幻の女、とは私のいつもの妄想。

中之坊の外観、こんな感じ。
中之坊は當麻寺の塔頭の要なのです。

「ここ、ママの庭ってことは、おらの庭でもあるよね」

日本最古の鐘楼。もちろん国宝。當麻寺、何気にお宝だらけ。

ああ、私のいちばん古い記憶、私のいちばん最初の記憶、二上山、私の魂の産屋(うぶや)。

當麻寺から東、ほぼ直線上に三輪山が。
太陽の道なりなのです、大和盆地は。
そう、こんなところに生まれ落ちたが最期。
私は生まれてから死ぬまで考え続ける、太陽が生まれて、死んで、必ずよみがえることを。

道の駅ふたかみパーク當麻へ。
ここは地元の主婦の方々お手製のお惣菜が美味しくて大人気なのです。
息子は五平餅に夢中。

私の一押し。小麦餅。物心つかないころから食べています。私の実家では「けはや餅」と呼びます。

このお餅を食べると、夕陽が沈む二上山を無心で眺めた子どものころに戻ります。
無心だった、あのころへ。
おれはまだお前を……思うている。おれはきのう、ここに来たのではない。それも、おとといや、其さきの日に、ここに眠りこけたのでは、決してないのだ。おれは、もっともっと長く寝て居た。でも、おれはまだ、お前を思い続けて居たぞ。
折口信夫『死者の書』
姫の俤びとに貸す為の衣に描いた絵様は、そのまま曼陀羅の相を具えて居たにしても、姫はその中に、唯一人の色身の幻を描いたに過ぎなかった。併し、残された刀自・若人たちの、うち瞻る画面には、見る見る、数千地湧の菩薩の姿が、浮き出て来た。其は、幾人の人々が、同時に見た、白日夢のたぐいかも知れぬ。