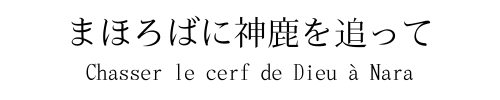『日本書紀』の立役者は藤原不比等です。
聖徳太子像を描き上げ、蘇我氏を朝敵に仕立て上げ、持統天皇の懐刀としてこの国を思うがまま動かした。
ともあれ、不比等が日本の礎を固めたことに誰も異存はないでしょう。
不比等は天智天皇の落胤との説があり、これは周知の事実として罷り通っていたのでしょう。
世が世なら、不比等は正当な立場で天皇の地位にあったかもしれない。それができない存在ではなかったので。
不比等の子どもたち、光明皇后や藤原四子の専横は、そこが基になっているのでしょう。
山岸凉子先生の『日出処の天子』でも、聖徳太子となった厩戸王子を「名ではなく実を取ったのだ」と、物語の終盤で王子の真意を掴んだ蘇我馬子が息を吞んで、呻きました。
名を捨てて実を取る。不比等と太子は似ています。

聖徳太子と法隆寺の興隆は太子信仰者の橘三千代の存在が大きいというのも、感慨深いものがあります。
宮廷をひそやかにしめやかに掌握していた三千代、持統から続く天武の皇統の天皇すべてから信頼を勝ち得ていた、その徹底して分を弁えた賢明さ。
長屋王と、その妻の吉備内親王、4人の息子ともども自殺に追い込まれた。
三千代はこれをどう思っていたのか。
藤原四子が消したかったのは、長屋王以上に血統の良い、天智と天武と持統と元明の血を引く吉備内親王とその息子たちだと、三千代はすぐさま気取ったに違いない。何よりも、持統の3人の孫、元明の3人の子、元正と文武とそして吉備内親王を養い育てたのは、三千代そのひとだった。
1歳にならずして亡くなった聖武と安宿媛の皇子、基王の復活を、三千代はこれほど求めた瞬間はなかったのでは。
みこさまが存命であらせられたのなら、このような始末、起こり得るはずもなかった。
藤原四子だけの罪ではない。三千代は、自分が育てた聖武と自分の娘である安宿媛の無辜を認められるほど、愚かではなかった。
天皇家のゴッドマザーとして三千代は誰よりも、聖武の血統の不安定さを熟知していた。
天智と天武の血統は傍系なり何なり続いているが、持統の血統は実質これで絶えたようなものだと、長屋王の変で三千代は観念したのかもしれない。
持統様はいつか、「私は五歳で死んだようなもの」、そう静かに仰った。
三千代の実力を真っ先に認めたのは鸕野讃良皇女、持統天皇だった。
聖武天皇からは、持統天皇の気質をうかがえない。
殺されたに等しい吉備内親王は、その姉の元正と並ぶほど、藤原氏から脅威を抱かれる存在であったのに。
三千代は、藤原氏と自分とは、やはり異なる流れにあると、重ねて思い知ったのでは。
あのひとが生きていたら誰もこんな軽はずみで場当たりな暴挙には打って出なかった。
9年前に不比等が亡くなったときから、ゆがみ始めた、すべては。

あのひとがいない、もう、この世のどこにも。
晩年、仏への祈りに明け暮れた三千代の心中に去来するものは、絶対の不在、それだったのではないでしょうか。