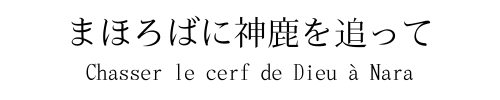奈良国立博物館の展示で、愛媛県川之江市(現在の四国中央市)出土の弥生時代の銅鉾を観たとき、ふっと、悲劇の皇子の生涯を刻んだ本を思い出しました。
その本の題は『流刑の皇子』。
木梨軽皇子(きなしのかるのみこ)、記紀の悲劇の皇子が主人公です。
作者の阿久根治子さんは冷静と慈愛の双のまなざしで、「伝説は虚無から生じない」、「彼は懸命に生きてそして死んだ」、と声を荒げることなく詳らかにされるのです。
その昔、少女のころ、私は図書館でこの本を見つけ一読するなり、心を奪われました。
記紀に書かれていることは、きちんと証明されることばかり。
記紀の史実を捏造と嘯く人たち、机上論で茶を濁すんじゃなく、泥にまみれて現地を掘ってみればいい。
古代、飛鳥から天平にかけて激動の時代、記紀の編纂に携わった者は皆、命がけだった。
わが身を呈しても、刺し違えても、自分たちが生きた証を残そうとした。
いま現在、好き勝手にものを言う人が、はたしてそこまで心を尽くしているのか。
奈良大学通信の文化財学講読Ⅱのスクーリングで、講師の深澤先生はそう仰っていました。
深澤先生から教えていただいたこと、わが血肉と化した、生きた教えです。
さて、『古事記』では、軽皇子と衣通姫(そとおりひめ)は同母兄妹による禁じられた仲を断罪されて流され、四国の地で共に死んだと描かれます。
めまいがするくらいの悲恋です。
これ、『日本書紀』では、允恭天皇の息子が軽皇子で允恭天皇の皇后の妹が衣通姫、そう関係性がねじられ、権力闘争が主旋律になっています。
記紀の相違点は、読み手の元正天皇と文武天皇が同母姉弟だったからかな、とは私の独断。
さても、悲劇を貫く皇子と皇女の心中立(しんじゅうだて)、『古事記』が『日本書紀』を凌駕しています。
同腹の兄弟姉妹の恋愛、実はそんな禁忌でもありません。軽皇子の政敵である安康天皇と長田皇女が、先ず、そう。
衣通姫が巫女的存在で、その神性を穢したことによる罪過、これもどうかな? です。
衣通姫は、国家権力に肉薄した存在であった、これが真相でしょう。
国家権力に肉薄した男と同格の、父母とも同じくする姉妹である蓋然性、当然高い。
さて、決定権を持つ女、他にもいます。
天智天皇と間人皇女、大伯皇女と大津皇子、二組とも、恋愛関係にあったでしょう。
国家そのものである伊勢神宮、その斎宮である大伯皇女は言を俟たず、間人皇女も先の天皇の皇后、何人も冒せるべき存在ではない。
これが、処女性に紐づけられる程度の職能とは異なる所以です。
間人皇女と大伯皇女は、国に嫁いだ女。
だから、手を出した男は首が飛ぶ。
さすが天智天皇こと中大兄皇子、その点、用心深かった。
しかし、大津皇子は叛逆者として公に振る舞うかの如く、堂々と伊勢に姉を訪ねた。
会うだけでも殺される、それでも会わずにいられなかった。
姉にしてみれば、生きて二度と会えないはずの弟が会いに来てくれた、つまり、それは、恋の成就と身の破滅が同時に訪れたということ。
弟は姉に、命を呈しても会いたい人に、叛乱を誓いに向かったのか、愛と別れを同時に告げたは異存なく。
姉は、弟を撥ねつけるべきで、そうすることも可能だった。
しかし、姉は、弟に扉をひらいた。
勇気をもって退路を断った弟を、この瞬間だからこそ、姉は庇護した。
斎宮として国に嫁ぎながら、生身の男を受け入れた。
叛逆者として、国を裏切った女として、八つ裂きにされてもかまわない。
命がけで自分に会いに来てくれた、そんな相手と一緒に死ねる、本望だと。
大津皇子の死と共に、大伯皇女の魂も冥界へ。
もう生きている意味などない。
それでも姉が生を全うしたのは弟に乞われたからではないでしょうか。
生きていてください。
私はあなたの心に生き続けます。
だから、死なないでください。
生きていてくださる、ただそれだけでいいのです。
伊勢路は、死出への旅路です。
男も、女も、命をかけたのです。

宇都曽見乃人尒有吾哉従明日者二上山乎弟世登吾将見
うつそみの人なるわれや明日よりは二上山を弟世とわが見む
この世の人である私は、明日からは二上山をわが弟と見ようか。
大伯皇女『万葉集』2-165
二上山のふもとの町に生まれた私には、その頂に掲げられて眠る大津皇子は好悪の感情を超越した、身内のようなものです。
バカタレな皇子、涙が出る。
正々堂々にも、ほどがある。
想えば想うほど切なく、たまらなくなる身内です。
軽皇子と衣通姫を物語るつもりが、二上山の姉と弟を浮上させてしまい。
けれど、遠からずもないでしょう。
佐佐波爾 宇都夜阿良禮能 多志陀志爾 韋泥弖牟能知波 比登波加由登母 宇流波斯登 佐泥斯佐泥弖婆 加理許母能 美陀禮婆美陀禮 佐泥斯佐泥弖婆
笹葉に 打つや霰の たしだしに 率寝てむ後は 人は離ゆとも 愛しと さ寝しさ寝てば 刈薦の 乱れば乱れ さ寝しさ寝てば
あなたと添い遂げた今、もう二度と離れることはできない。
『古事記』下巻 允恭紀
たとえ全世界を敵に回しても。
『古事記』に名高い軽皇子の夷振之上歌(いなぶりのあげうた)を、私なりに超意訳。
身を滅ぼす恋をするために生まれてきたような若い魂。
うらやましい、そう素直に思えます。
まっすぐ誰かを好きになって、相手も自分の気持ちに応えてくれて、それだけで幸せで、もう死んでもいい、そう思える瞬間を人生で与えられる、それこそ、神に愛でられたに等しい。
人生は意義ある悲劇だ。それで美しいのだ。生き甲斐がある。
岡本太郎『壁を破る言葉』
こんな魂を揺さぶる叙事詩が残された国、それが日本なのです。
謙遜することなく、ただ喜ばしい。
この国に生まれて、この国の歴史と文化に育まれて。
「文化を守る」ということは、「おれを守る」ということだよ。
三島由紀夫
『文武両道と死の哲学』福田恆存との対談