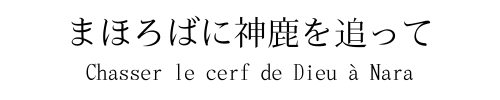すみれの花の砂糖づけをたべると
私はたちまち少女にもどる
だれのものでもなかったあたし江國香織詩集『すみれの花の砂糖づけ』
私の大切なひとの何人かは、50年も満たず、もしくは50代の渦中で、永遠の旅に立ち、私自身、彼らごと死を想って生きている。
私は随分前から容貌がほぼ変わらない。年老いた自分が想像できない。否、否、年老いた自分がどこにもいない。だから、見えない、春の霞んだ空、それしか。
むかし、花の盛りの桜烟る春霞のもと、「瓊花さん、握手しよう」、去り際にいきなりそう言って、私の両手を取り、骨がきしむくらい強く握りしめ、それでも笑って道を分かれた先生は、それからまもなく男の盛りの40代で逝ってしまった。
「死ぬことを無視して生きていけるだなんて、さらさら思っていないだろう、瓊花さん。だから俺は瓊花さんと話すのが、好きだった」
私だって、好きだった。

「瓊花さんあなた、痩せたね」
「春になると、逝ってしまったひとのこと、思い出してしまうんで」
「いい男だったね」
「年々、逝ってしまったひとが近くなる」
「やめなさい、あなたらしくない」
「本当のこと言ったまでですが」
「あなたは自分で思っている以上に影響力がある。僕ですら、視界が霞みそうになる」
「僕ですら。ああ、いやだ、男なんて」
「死んだ男はいやじゃないくせに」
「死んだ男は、いい男、です」