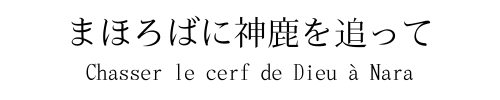何が欲しいのと 訊かれたら困るわ 何を望めばいいの 幸せ 不幸せ
いつか幸せが 訪れたとしても 哀しい日々をきっと なつかしむに決まってるあなたの悩みなんて 取るに足りない 大げさなだけよ
望みが美しいのは それが満たされぬうちだけなのよ生まれてくるときも 訊いてくれなかった 生まれてみたいのか それともやめたいか
ひとり都会のなか 歩いているときも 誰も尋ねはしない 都会が好きかどうか部屋のあかりを見る ドアごしに ガラス窓ごしに
私は待っているの ただ待ち続けてるの 何かをWenn ich mir was wünschen dürfte
Friedrich Hollander私が何か望んでいいとしたら
選曲・訳詞 加藤登紀子
編曲・演奏 坂本龍一
作家の塩野七生さんはご自身を「ヨーロッパ育ち」と自嘲も兼ねて象られた。私は24歳のとき、たった1か月だけイタリア半島で遊んだだけの俄ではあるけれど、3歳のころからアレクサンドロス大王と馴染みのように知己を深めて生きてきたので、南北アメリカ大陸よりユーラシア大陸の西の果て、ヨーロッパに親和性を懐かないわけがない。
私が生まれた年に制作されたイタリア映画、『The Night Porter』は、ナチスの収容所で出会った男女が過去に我が身もろとも巻き戻すかのように破滅へ向かう、その触れてはならない「人間の本能」を描いたがゆえに焚書ものの扱いだったけれど、その危うさを描き切った女性監督リリアーナ・カヴァーニの勇気を称えるかの如く、イタリアのみならずヨーロッパ映画界の重鎮たるルキノ・ヴィスコンティを始めとした識者の擁護によって、世に出た名作。

あの映画の舞台はウィーンで、私はヴェネツィアの街をさまよっているとき、ここからならオーストリアも8時間ほど電車に揺られれば着くのだと知り、陶然となった。
行ってはいけない。そう何か、私を圧し留めるものが脳裏を掠めなければ、行っていただろう。
私は若く、ただでさえ若く見える日本人のなかでも私はさらに若く見え、イタリアではどこへ行っても「pupa」もしくは同じ意味でフランス語の「poupée」つまり「お人形さん」と呼ばれた。
たぶん、イタリアとその半島に漂うヨーロッパの人びとは、私を「少女」へ揺り戻す「おとな」として、私をぞんぶんに甘やかす存在であったのだ。

あの映画のなかでも、収容所に囚われた少女のときに与えられたものに似たドレスを、ウィーンの街で思わず買い求めてしまった20年後の女、その、「失われた光と闇」を追う姿に、私は言葉を失った。
私も、ヴェネツィアで、あの女と同じように、少女のころに身にまとっていたものに似たレースの白麻のブラウスを、手に入れずにはいられなかった。
私には、ヨーロッパは、私自身の未熟さを思い知らせてくれながらも、その両腕で包んでくれるだけ包んでくれる、「おとな」、そのものだった。
あの1か月が、最後の日々だった。
私が「少女」として過ごせた――