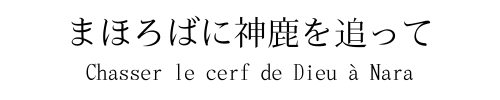緒形拳さん主演映画『将軍家光の乱心 激突』、この1989年バブル経済末期の作品、ざっくりとあらすじを述べれば、乱心した徳川三代将軍家光が世継ぎの竹千代の暗殺を計画する、それを緒形拳さん扮する刑部を筆頭とする7人の浪人たちが抗い討ちながら、竹千代は父将軍のいる江戸へ向かうという、和製スターウォーズめいた活劇です。
緒形拳、千葉真一、丹波哲郎、長門裕之、松方弘樹と、昭和の名優の満漢全席、おなかいっぱい。
で、アクション時代劇はさておき、私が意識を留めたのは、味方が一人二人と死んでいく様に気落ちした竹千代の「我らは負けたのか?」との問いかけに、刑部の「若子(わこ)が生きておられる限り、我らは負けではない!」との答えに、「余が生き続ければ、我らの勝ちか!」と竹千代が断言するシーンです。
私は、すさまじい記憶の回帰に、マドレーヌを食べたプルーストのように冴え冴えとした幸福感で満たされました。
貴種を御旗に掲げて戦う。これは日本史に限らず歴史の当然です。
で、私はこどものころから、貴種の方々は自分のために命懸けで戦っている下々の者をどのように見ておられるのだろうか、と懸念しておりました。
「あやつら勝手に戦って、勝手に死んだ」とか貴種の方々が舌打ちしていたら、下々はやってられないよな、と。
その反面、阿鼻叫喚の戦地に人質同然に連れ込まれ、天命尽きれば全滅にまで巻き込まれる、そんな貴種の方々のやるせなさも看過できない、とも思えました。
それを踏まえ、上記の竹千代の言葉。
なんだかもう、グッときました。

私が歴史上の人物で尊敬する方、ふたり。
ひとりは鑑真和上。
もうひとりは、後醍醐天皇第一皇子、尊良(たかよし)親王。
鑑真さんにつきましては、何も言うことはないと思います。
で、尊良親王について。
この方の死にざまはこの方の生きざまそのもので、私もできるならこんなふうに人生の幕を引きたいと寝ぼけたことを願ってしまうほど、心臓を射貫くものなのです。
南北朝時代、越前金ケ崎の戦い。
足利軍による一冬にも渡る地獄絵図さながらの兵糧攻めに遭う中、新田義貞の息子の義顕が留守居の大将を務めていました。
(この戦について、総大将の義貞みずから陣を離れたという有り得ない事実、情けなくて情けなくて、仕方ありません。
軍事責任者の戦線離脱、どんな理由も罷り通りません。
新田義貞という男、悪い人間ではありませんが、こういった度しがたい詰めの甘さには、目も当てられません。)
しかし、若い義顕、持ちこたえられず。
自分はその命でもって敗戦の責任を負うけれど、武者ではない尊良親王へは敵への降伏を、義顕は進言したのです。
「宮、生き延びてください」、と。
すると尊良親王は常にも増して朗らかに笑いました。
(世論の集大成である『太平記』にそう描かれるということは、いつも笑顔、優しい方だったのでしょう、尊良親王は。だから、武闘派の父帝には後継者と認めてもらえなかったのかもしれません。)
「元首とは、股肱の臣あってこそ。義顕、そなた失くしてどうして私が元首でおれる。なあ、共に冥土で、この戦の仇を討とう。
さて、いかにも私は武者ではない。自害とは、どのようにするのかな? 教えてくれまいか」
……こんな凄惨な状況なのに、まるでみんなの心を和ませるように、爽やかに励ますように教えを乞われたら、「一緒にいるよ」と同行を約束された義顕でなくったって、誰だって号泣しちゃうよ! ……です。
「宮、自害とは、このようにいたします」
もう顔中を濡らす涙もぬぐう必要もないと、二十歳の義顕は見事に自刃して果てました。瞬きもせずその若武者の最期を見届けた後、三十歳の尊良親王もそれに粛々と倣いました。
300名の家臣も二人の跡を追い、火が放たれた城は、真冬の北陸の凍える雪の降る中、陥落しました。
越前金ケ崎城、まだ訪ねたことがないのですが、必ずお参りに行きたいと願っています。

尊良親王は、自分の立場をほんとうに弁えた方でした。
人の上に立つ、その意味の真実を知っている方でした。
最期の最期、下々こそ慮る方でした。
骨と皮に痩せ衰えた随身の者たち、彼らを単純に尊良親王は見捨て置けなかったのかもしれません。彼らはいつも自分を第一に扱ってくれた、それに胡座をかくような無情な人間ではなかったのです、尊良親王は。
何より、数えで11歳の竹千代とちがい、尊良親王は「おとな」でした。
生き残った竹千代と、皆と一緒に死んでいった尊良親王は一見真逆に見えますが、人を信じる、その心は同一です。
地獄に等しい絶望のさなかでも、尊良親王は普段以上の満面の笑みで応じる方なのです。
「そなたたちあっての私なのだよ」、と。
「仁」とは、尊良親王こそ表す言葉でしょう。
尊敬するひと、尊良親王。