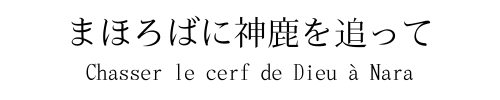櫻花 開哉散 及見 誰此 所見散行
桜花咲きかも散ると見るまでに誰かもここに見えて散り行く
桜の花が咲いては散るかと思われるほどに、いかなる人々が、ここに現われては散りぢりに別れゆくのだろう。
柿本人麻呂 『万葉集』 12-3129
桜を愛した日本人。たくさんの歌人に詠まれた桜。
私は、この、歌聖と謳われた柿本人麻呂の、しんと染み入る桜の歌が、いちばん好きです。
桜の咲く散るは、人の生き死に。
咲くも生きるも、散るも死ぬも、人麻呂は同じ目線で等しく描いています。
桜の花弁ひとひらずつに、たましいがひとつずつ、灯るような。
春、命が入れ替わる季節だからこそ、すぎゆく者を見送った歌なのかもしれません。

全身全霊を三十一文字に結晶させた人麻呂の歌を詠むと、ぽんっと、宇宙に投げ出された気がします。
自然は、摂理は、人麻呂の心身を得て、私に降り注がれた雨か、光か。
ただ、人麻呂の孤独は、私の孤独でもある。

人麻呂は、その人生で一瞬でもかかわったものをたやすく忘れ去ろうとはしない、生きとし生けるものを愛したひとでした。
だから私を含めた多くの人々が、人麻呂の存在をその歌ごとひっくるめ、愛してやまないのでしょう。
いまはむかし、コロナ禍の寧楽の都の春、西行や紀貫之の爛漫とした桜ではなく、人麻呂の粛然とした静けさの桜が、音もなく咲きこぼれていたものでした。