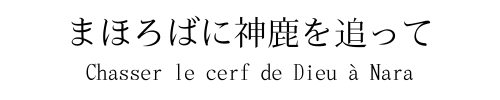2019年3月26日、風呂場で『エメラルドの伝説』を歌いながら、泣きました、おんおん、と。
ショーケン、萩原健一さん、大好きでした。
あこがれ、でした。
ショーケン主演、大杉漣さん、根津甚八さん、奇しくも鬼籍に入られた方ばかり、私の大好きな俳優さんが揃い踏みの20年以上前に放映されたドラマ『テロリストのパラソル』をYouTubeで再見すると、ほんとうに昭和が平成がまたたくまに遠くにいってしまう、意識がかすむようでした。

90年代、二十歳前の私は、奈良県橿原市今井町の風雅地区の近くの音楽喫茶「山(やま)」に、京都出身のボーイフレンドと訪れました。
彼は、今から思えば、ショーケンっぽい煤けた空気を、その心身にまとわせていました。
「山」は紡績工場跡であって外観は至って殺風景、それが一歩中へ入れば息をのむ、重厚なジャズホール。
コンサートホール並みの音響で、音楽が店中に充満していました。
壁の書架は、五木寛之の本で埋められていました。
私たちはストレートの紅茶を注文、誰に示唆されるまでもなく、ふたり小声で言葉を交わしました。
彼の若くして亡くなった叔父さんは京都の名門大学で学生運動に燃えて、燃えて、燃え果てたそうです。
70年代生まれの私も彼も、影も形もなかった、全共闘時代。
「瓊花はあの時代に生きてたら俺の叔父と同じ道を辿ってるやろね」
彼はそんな恐ろしい台詞を平気で放り投げてくる青年でした。
「あたしは、右も、左も、わからへんわ」
私が吐いた捨て台詞を彼は難なく拾いあげ、吹き返しました。
「でも、沙漠は好きやろ、瓊花。沙漠ったら、右も、左も、あるもんか」
私は絶句しました。
私は当時、三島由紀夫を乱読していました。『午後の曳航』がいちばん好きでした。
昭和の叡智であった三島由紀夫ですら砂を噛むような全共闘の観念。
ああ沙漠、沙漠。
「奈良はガツガツしてへんから落ち着くわ」
彼は笑って、京都へ帰っていきました。
当時の私の髪型はロングのワンレングスで、アラブに渡った革命の女王に、やはり似ていました。
ところが思想など私には、かけらも備わっていない。
けれど、私も持っている、私を。
それから私は五木寛之の小説をがむしゃらに読みだして、『四季・奈津子』だったか、「透明な紅茶を牛乳で濁す残酷さ」、その一文に心臓を射抜かれ、牛乳を先に器へ、後から紅茶を器へ、ミルクティーの注ぎ方も変えました。
そう、濁されるのではなく、濁っていく、みずから。
いまも「山」はそこにあります。
音楽喫茶なのに流れる曲はまるで耳に入って来ず、そこでは私も彼も奢りの若さで、赤く澄んだストレートの紅茶に唇をひたし、睨み合っているのです。
あれは恋ではなかった。
憎しみだった。

このおもちゃの指輪、息子が3歳のとき、保育園の夏祭りの市場で私に選んでくれました。「ママ、エメラルド、好きでしょ」と。
市場を担当していた女子中学生たちが「自分のもの買わないで、お母さんにプレゼントするの! 僕なんてやさしいの!」と驚嘆していました。
私は息子が赤ちゃんのころからザ・テンプターズの『エメラルドの伝説』を歌い聴かせ、いつも保育園の帰り道、ふたりでショーケンになりきって、ちからいっぱい、歌っていたものです。
遠い日の 君の幻を
追いかけても 空しい
逢いたい 君に逢いたい
緑の瞳に 口づけをザ・テンプターズ『エメラルドの伝説』
作詞:なかにし礼 作曲:村井邦彦