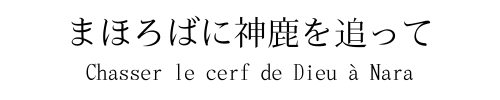久しぶりにヘミングウェイの『インディアン・キャンプ』を読み直してみました。
邦訳にして10ページにも満たない短編ですが、傑作中の傑作です。
主人公のニックが医者である父と叔父のジョージと釣り目当てに湖でキャンプを楽しんでいたが、原住民(小説ではインディアンと称す)の妊婦が産褥で3日も苦しんでいると知らせを受け、その村を訪れる。
父はジャックナイフと釣りの糸と針で妊婦へ帝王切開を施し、そこへ息子のニックに立ち会わせる。
母親と子どもは無事だったが、しかし、なぜか、インディアンの父親はのどを裂いて自殺していた。
ニックは、「自分は決して死なない」と、感慨を擁いた。
上記、ざっくりと『インディアン・キャンプ』のあらすじ。
インディアンの父親はなぜ「自殺」したのか、ニックはなぜ「自分の不死」に考え到ったのか。
このふたつが、ヘミングウェイが残した、澄み切った謎。
ジョージ叔父がインディアンの母親と通じていてその子どもの実の父だった、そういう説もありますが、私はそんなメロドラマをここでヘミングウェイが書くわけないと初見から思っていました。(メロドラマは悪いものではなく、ただ、この小説にはふさわしくないというだけです。)
だからといって、確たる結論も見当たらず、それらは初見の前世紀から意識に沈殿する謎であり続けていました。
しかし、高野泰志氏の論文「麻酔の認識論『インディアン・キャンプ』をめぐる帝国の欲望」、これが私の積年の謎を解決へ一歩進めたのです。
ニックの父は、そこに持ち合わせていなかったとはいえ、インディアンの妊婦に麻酔なし(!)で開腹手術を行ったのです。なぜなら1920年代のその当時、原住民たちは痛みに強いと見なされ、麻酔は文明人に用いるもの(!)と認識されていたからです。
そして、原住民は自他の境界を曖昧にして自然を受け入れるため、インディアンの父親は妻と同じように産褥を味わう「擬娩」のさなかに、ジャックナイフで腹を切り裂かれる空前絶後の痛みゆえに「自殺」した、と。
確かに出産は命がけで、女のおかれた状況に対するに、男は喉を引き裂いて同等でしょう。
ニックがこぼした言葉「自分は決して死なない」は、インディアンの父親の自然崇拝の擬娩の果ての自殺となった姿に、妻の苦痛を解放させる意味を悟り、インディアンの父親が自然に循環されたと捉えた証に、「その場に立ち会ったニック自身『も』決して死なない」と考えられる、と。
私は、この高野先生の説に、甚く感銘を享けたのです。

ああ、我らがヘミングウェイ、その簡素極まりない文体から浅く見られがちですが、その詩のような文体はまさに詩そのもので、ゲーテが『詩と真実』を物したように、謎は、詩は、つまり言葉としての真実は、はるか湖の底の底にまで落ち込み、密やかに、ただ地球に、つまり現実としての真実に溶け合っているのです。
ヘミングウェイの神話。
アメリカの神話です、ヘミングウェイが語る「真実」は。